2009.12.01鉄道テツペディア Vol.20 「列車の暖房」
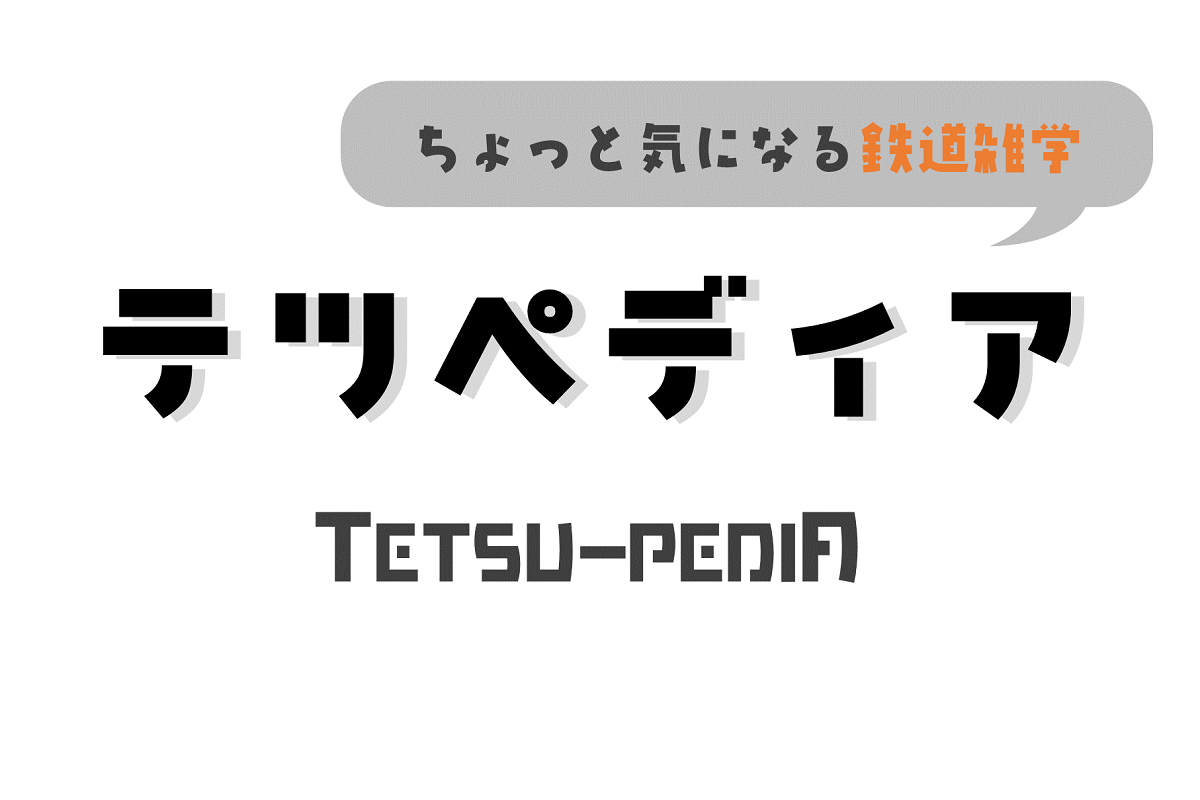
ちょっと気になる鉄道雑学
鉄道にまつわる「知ってトクする豆知識」を紹介するコーナーです。
寒さが徐々に厳しくなって冬本番を迎えています。仕事も忙しくイベントも多い年末年始、もし移動時の車内に暖房がなく冷えていたら…と思うと、鳥肌が立ちますよね。
今回は、私たちをほっとさせてくれる「列車の暖房」について見ていきましょう。
列車の暖房の歴史
1 SL時代
日本の鉄道黎明期、蒸気機関車が主流だった明治時代初期。蒸気機関車に牽引されていた客車の暖房は、最初は湯たんぽや、石炭によるダルマストーブが一般的でした。しかし、温度設定の手間や火災の危険が大きいことから、明治時代後期には、牽引する機関車から供給される蒸気で客室を温める蒸気暖房が主流になっていきました。
もともと蒸気暖房は、列車が走るために作られた蒸気の一部を、蒸気機関車から客車へと送るもの。蒸気を発生させるのは、蒸気発生装置です。燃料には重油や軽油が用いられ、これが当時の列車暖房の主力となりました。
2 電気機関車時代
1926(昭和元)年に東海道本線・横須賀線間が電化されると、蒸気機関車ではなく電気機関車が客車を牽引するタイプが登場しました。当時の客車は蒸気暖房に対応している車両が多く、電気機関車に蒸気発生装置を搭載し、客車に蒸気を送るようになりました。
また、蒸気機関車から電気機関車への置き換えが進むと、電気機関車の後ろに暖房専用の蒸気機関車を連結したり、石炭のボイラーを搭載した暖房車を連結するなどして客車に暖房を送るようになりましたが、列車編成が長くなる、列車重量が重くなるなど非効率であったため、次第に電気機関車に暖房用電源を搭載する電気暖房へと替わっていきました。それらの列車では、機関車からそれぞれの客車へ、直流1,500V電源を供給し暖房を行なっていました。
 国鉄時代の暖房車
国鉄時代の暖房車
戦後の客車では、編成の一端に電源車を連結し電源車が編成内の冷暖房や照明など一切の電力を供給する集中電源方式と、編成内の車両に一定の割合で床下ディーゼル発電機を設置する分散電源方式が採用されました。供給する電源は、それぞれ交流600Vと交流440V。後者は、1950年代後半から置き換えが進展した電車における電気暖房と同じ大きさの電力です。
3 電車時代
1950年代後半には、機関車から電車への置き換えが進展し、機関車や電源車が採り入れた電力を客車に供給する方式ではなく、各客車がそれぞれに集電した電力で暖房を行なうことが可能となりました。
現在の電車は、パンタグラフや集電靴により架線や第三軌条から採り入れた電気を、座席下の電気ヒーターに通電して発生するジュール熱で車内を暖房しています。
 山手線の暖房ヒーター
山手線の暖房ヒーター
 中央線の暖房ヒーター
中央線の暖房ヒーター
以前は、採り入れた直流電力1,500Vを変換せずそのままヒーターへ通電していましたが、現在は、電動発電機や静止形インバータによって三相交流400~440Vに変換した電気を通電し電気暖房を行なっています。
多くの電車では暖房ヒーターは座席下に設置されています。冬の車内で、足がポカポカ温かいのは嬉しいですよね。一方冷房装置は天井側にあり、列車の冷暖房は、暖かい空気は上へ、冷たい空気は下へいくという自然対流を利用した合理的な仕組みになっていることが分かります。また、JR東日本の山手線や横浜線などに連結されている6扉車(1車両に扉が6つある)では、座席下の電気ヒーターだけでなく、床暖房も使用してバランス良く車内を暖めています。
列車の暖房のエネルギーは家庭用の約10~12倍もあります。列車では家庭に比べて人間が多く扉の開閉が多いため、より大きな電力が必要となるのです。
同じ電気暖房でも、いろいろと種類があります。
火気や可燃物を使用せず車内の空気も汚さない、合理的な暖房なのですね。
- ※掲載されているデータは2009年12月現在のものです。
- ※写真協力:交通新聞サービス
