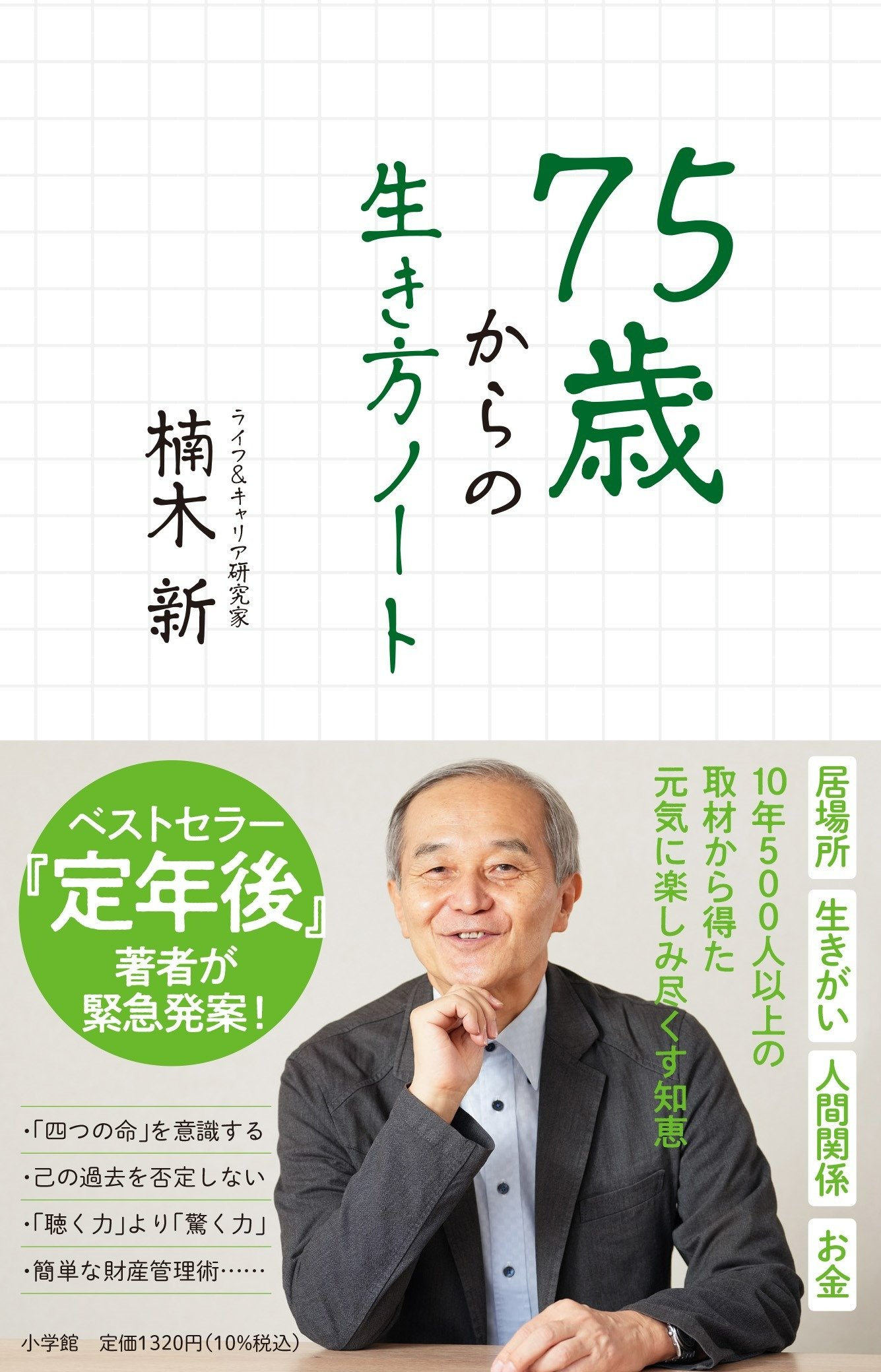2024.08.15ジパング俱楽部人生後半戦をアクティブに「やりたいことリスト」を作って人生を豊かに!|解決! 60代からのお悩みごと
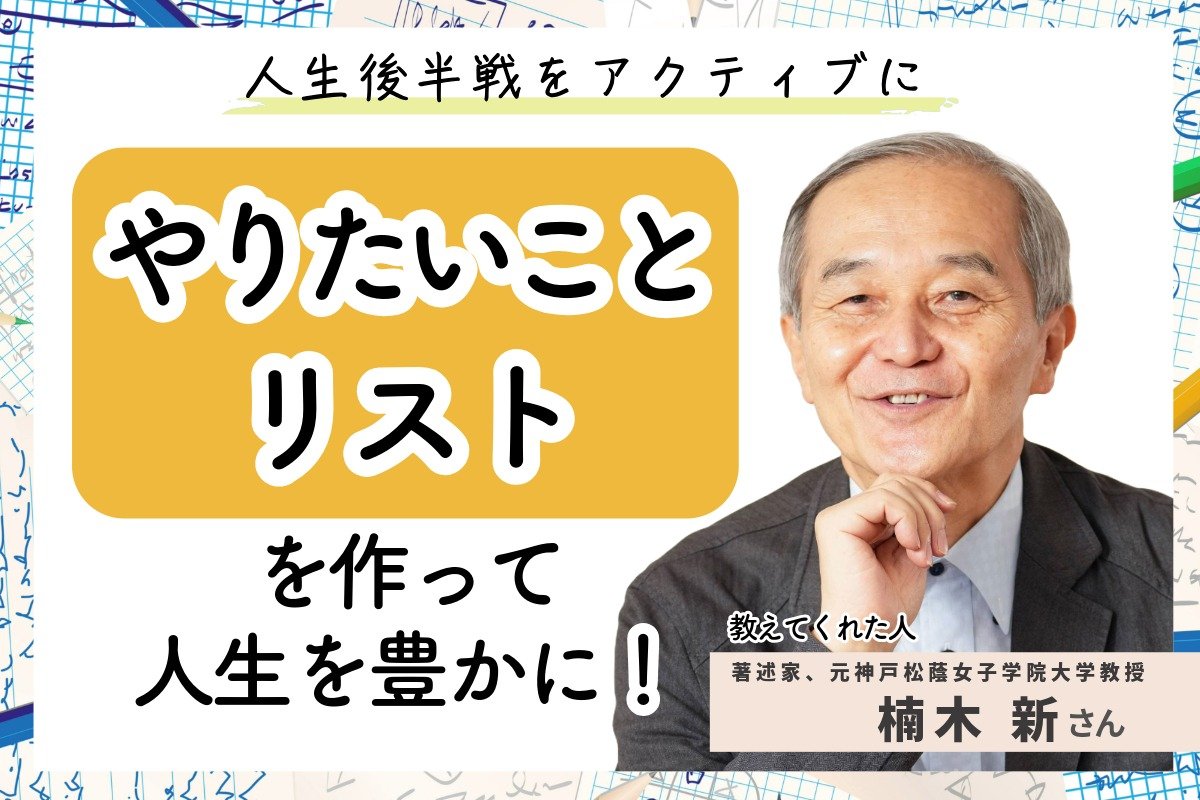
やりたいこと、できていますか?
「いつか○○へ行ってみたい」「○○に挑戦してみたい」と思いつつ、なかなかきっかけがつかめず実行できない……。そういうジパング世代の方も多いのではないでしょうか。
ベストセラーとなった『定年後』の著者で、人生後半戦の過ごし方について500人以上に取材してきた楠木新さんは、「エンディングノートではなく、リ・スターティング(再出発)ノートを作ってみよう」と提唱しています。
35年以上の会社員生活をリタイアし、自分自身の「やりたいこと」を考え実践してきた楠木さんに、お話をうかがいました。
教えてくれた人
1.「リ・スターティングノート」とは?
よく人生最後に「エンディングノート」を書こう、と言われますが、それではもったいない。私は、終わりではなく、今から新しいことを始めよう、やりたいことをどんどんやろう!という「リ・スターティングノート」をすすめています。
2017年に出版した『定年後』では定年前後の人たちに取材したのですが、最近話を聞いているのは60~70代の方たち。みなさん、とてもお元気です。この年代は仕事も一段落し、自由時間が増え扶養義務も軽くなっている。私はこの時期を「人生でもっとも輝ける期間」だと思っています。
そう考えるようになったのは、会社員として働いていた40代半ば頃、「人生後半戦、このままでいいんだろうか」と悩み始めたことがきっかけです。
私は神戸の歓楽街で育ったんですが、周りには商売人や職人、アウトローの大人たちがいたんです。お笑いの「神戸松竹座」も近くにあって。それが大学卒業後は生保会社でサラリーマンになって、若いうちは仕事も新鮮で楽しく働いていました。

でも40歳の時に阪神・淡路大震災に遭遇して、40代後半で体調を崩し休職したこともあって、「これからどうしていこうか」と将来について本気で考え始めたんです。
そんな時、夢にこどもの頃慣れ親しんだアウトローのおっちゃんたちが出てきた(笑)。
彼らは他人の言うことは聞かずに、思ったことを発言して自分の足で立って生きている。一方で、サラリーマンは安定しているし、給料も定期的にもらえる。でも、自分が大切だと思うことを自由に発信する、ということは難しかったんです。
定年後、どう生きていくか?
そこで、みずから発信するにはどうしたらいいか、定年後はどう過ごしたらよいのか考え始めたんです。会社に勤めながら50歳から、会社員から別の職業に転身した人たちや定年後に新しいことを始めた人たち150人ほどに話を聞きました。60歳で定年退職した後に、それらのインタビューを中心にまとめたのが『定年後』です。
中高年以降の会社員は、今後どのように過ごしていけばよいか迷っている人は多い。しかし彼らに適切な情報や機会を与えている人はほとんどいない。だったら、彼らが「いい顔」になるために実例を集めて情報提供する、それを自分の芸にしていこうと考えたわけです。
50~60代を中心に取材をした『定年後』を執筆した後、65歳~70代の方々に聞いた話をまとめたのが2023年に出版された『75歳からの生き方ノート』です。
2.まずは「やりたいことリスト」を作ってみよう
ただ、いきなり「リ・スタート」といわれても、「何をやったらいいのか分からない」「今さら新しいことを始めるのは自信がない……」という人もいるかもしれません。
まずは、自分がやってみたいことを書き出す「やりたいことリスト」を作るのがいいでしょう。作成の手順は、以下を参考にしてみてください。
「やりたいことリスト」の手順
- ※参考:『75歳からの生き方ノート』(小学館)
やりたいことの数や内容は、人によって違います。スラスラ書ける人もいるし書けない人もいるので、ひとつでも見つかったら大丈夫。探すこと自体が自分の人生の振り返りになります。
何より大切なことは、バッターボックスに立って自分でバットを振ること。つまり実際にやってみることです。そのためには、あまり先のことを考えるのではなく、この先2~3年で実現できそうな、小さくてもいいので具体的なことを挙げてみてください。
楠木さんはやりたいこと「R-1グランプリ」に挑戦
私の「やりたいことリスト」の最新の具体例をひとつ話すと、じつは今年2024年の初め、ピン芸日本一決定戦の「R-1グランプリ」(※注)にエントリーしたんです。小さい頃から芸人にも興味を持っていましたし、自分の講演をもっとおもしろくしたいと思って。
「定年退職者を探せ!」というネタを作って正月返上で練習しましたが、あえなく1回戦で敗退(笑)。でも、実際舞台に立ってみて「自分は演者には向いていない」ということが分かった。
じゃあ私は何に興味があるのかをもう一度考えてみました。私の関心はネタのおもしろさよりも、演者はどういう気持ちで芸に取り組んでいるのかということでした。
 「喜楽館」の演芸会で漫談を披露する楠木さん
「喜楽館」の演芸会で漫談を披露する楠木さん
私の生まれ育った神戸の新開地に「喜楽館」という上方落語の定席の演芸場があるんですが、そこで落語を聞いていると、マクラ(噺の導入部分)では自分が落語家になった経緯を語る人が少なくない。でもあまり深掘りはしていないんです。
そこで、落語家になった理由を直接聞いて発信すれば、興味を持ってくれる人が増えるのではないかと考えた。そこから「喜楽館」のホームページで「私が落語家になったワケ」というインタビュー記事を連載することになったのです。
R-1グランプリに出場したのがきっかけになって、新たな「やりたいこと」に出合った。興味を持ったことには挑戦してみる、バッターボックスに立つのが大事、と実感しました。
- ※「R-1グランプリ」は、吉本興業が主催するピン芸人の日本一を決めるコンクール。2024年のエントリー数は5457人。
3. やりたいことが見つからない時は?

やりたいことが浮かばない人は、「自分史ノート」から考えてみるといいですよ。
「自分が何をやりたいのか」を見つけるためには、自分と向き合うことが大事。
よく、生まれた時から現在までこと細かく文章に書く「自分史」が知られていますが、そういうものではなく、過去の自分の歩みから「自分が一番楽しかった時代」を思い出して掘り起こすのがおすすめ。
掘り起こしのポイントは3つあります。
- 1. 今までやってきた「仕事」から抜き出す
- 2. こどもの頃好きだったことをやってみる
- 3. 途中でやめてしまったことに再挑戦してみる
たとえば、学校の部活でやっていた剣道、若い頃夢中になったバンド活動、そういえば学生時代は物書きになりたかったっけ、などなど。
私の場合は、野球部に入って友人と映画館や演芸場をめぐった中学時代。だから芸名(ペンネーム)の「楠木新」は、中学の名前から付けたんです。
私が話を聞いた公務員の方で、小学校の通知表のコメント欄に「一歩前に出ない控えめな性格」と書かれていたのを思い出して、思い切って中途退職して職人の世界に飛び込んだ人もいます。当時の写真を取り出して、やりたいことを考えてみてもいいですね。
自分が一番充実していた頃のことを思い出すと、自然に「自分が本当にやりたいこと」に近づくことができるんです。
4.旅行に行きたいところ、やってみたいことをリストアップ

旅行好きなジパング倶楽部会員の方なら、「行ってみたいところ」「やってみたい体験」をやりたいことリストに挙げるのもいいですね。
私が聞いた話で、70代の女性が半ば夢だと思いつつ「オーロラを見てみたい」と言っていたところ、娘夫婦がいろいろ手を尽くしてくれて実現したそうです。
ひとりだと難しいなと思うことも、周りに言っておくとサポーターや仲間が登場して叶うことがあるんです。
だから、普段から「やってみたいこと」を公言しておくことをおすすめします。旅行は非日常を楽しむことなので、定年後の単調になりがちな日常生活のアクセントとしても最適です。旅行に行った後、体験を書いてみるというのもいいですね。FacebookなどのSNSで、旅の楽しさを家族や友人に伝えることもできます。
ただ私の周りでも、歳を重ねると「宿の食事が全部食べられない」「温泉に何度も入れなくなった」という嘆きの声も聞きます。行ける時に行っておく、これも大事なポイントです。
5. やりたいことを実現すれば、「いい顔」になる
私は昔から、人の「顔つき」に興味があったんです。会社で採用責任者だった時の面接も、転身した人に話を聞く時も、「いい顔」をしている人の話はとてもおもしろい。
自分が本当にやりたいことや自分に合ったことをやっている人は、「いい顔」になるのかもしれない。私は「いい顔」になるための3カ条をこんな風に考えています。
- 1. 好きなことを突き詰める
- 2. 他人に役立っているという実感
- 3. 新しい自分を発見する

たとえば、一生を映画に捧げた淀川長治さん。77歳にして「吉本興業」のお笑い芸人として舞台に立つ「おばあちゃん」。私は彼女の姿を見て、R-1への挑戦を決めました。好きなことを突き詰める人はいい顔をしています。
また、スーパーボランティアとして数多くの被災地に出向く尾畠春夫さん。自分にとって本当に大切なことに気づいた人や、自分が果たすべき新たな役割に目覚めた人は、みんないい顔をしています。
ぜひ、「やりたいことリスト」や「自分史ノート」を使って自分の大切なことを見つけ、人生をリ・スタートしてみてください。
まとめ
楠木さんに初めてお会いして、まず「穏やかで優しいお顔だな」と感じました。話が進むにつれ、2024年に挑戦した「R1-グランプリ」のこと、現在取り組んでいる「落語家になったワケ」の連載、生まれ育った神戸・新開地のおっちゃんたちの記憶……。まさに楠木さんの顔が、輝く「いい顔」になっていました。
さらに、「講演などの話でも、まだまだ頭の先で話している感じで聞き手の細胞にまで届いていない。もっとおもしろくできないかなぁと思って」と、先を見つめています。
やりたいことのある人は、みんないい顔になっていくのだな、自分も歳を重ねていくにつれて、いい顔になっていくといいな、と感じたインタビューでした。
文/綿谷朗子