2022.06.06鉄道【小説に鉄道を読む】穂村弘「幻想の鉄道ミステリー」
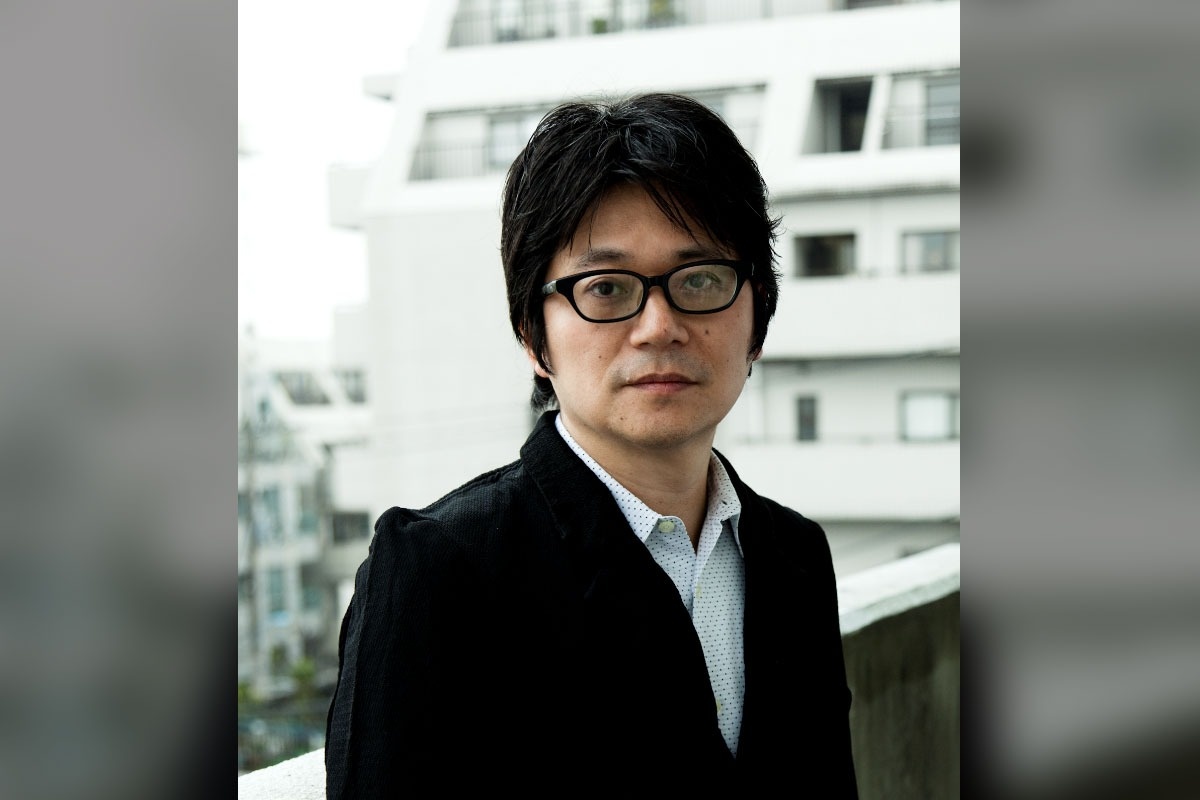

鉄道開業150年 交通新聞社 鉄道文芸プロジェクト
2022年10月14日の鉄道開業150年に向けて、交通新聞社で始動した鉄道文芸プロジェクト、通称「鉄文(てつぶん)」。さまざまな角度から「鉄道×文芸」について掘り下げます。
鉄文プロジェクト特別寄稿
鉄道を主題とした小説は数多くありますが、「鉄道の小説」と思われていない作品の中にも、鉄道に注目して読むと新たな発見がある作品がたくさんあります。また、「鉄道の小説」の王道といえる作品も、時を経て読み返すと新鮮な驚きに満ちています。
鉄道好きの人、小説好きの人だけでなく、今はまだそのどちらでもない人にも、思いもよらない形で身近な接点や関心の種を見つけられる小説があるかもしれません。
本記事は、「鉄道開業150年 交通新聞社 鉄道文芸プロジェクト」の一環としてスタートした「小説に鉄道を読む」特別寄稿シリーズの第1弾。歌人・穂村弘さんに、これまでの読書のなかから鉄道に着目していただき、その作品をご紹介いただきます。
著者紹介
幻想の鉄道ミステリー
「小説に鉄道を読む」というテーマを頂いて、まず思い浮かんだのはミステリーである。このジャンルには、『オリエント急行殺人事件』(アガサ・クリスティ)、『点と線』(松本清張)、『黒いトランク』(鮎川哲也)、『人形はなぜ殺される』(高木彬光)など、鉄道に関連する名作が多くある。ミステリーの舞台としての列車はいわば動く密室であり、また、犯人のアリバイと時刻表トリックは密接に結びついている。流れゆく車窓の風景や旅情といった非日常感も、作品の魅力を盛り上げる。
その中でも、今回は幻想的な鉄道ミステリーを挙げてみたい。時刻表を駆使したリアルなトリックは鉄道マニアには堪らないだろうが、私などはその緻密さについていけないところがある。自分の好みとしては、より現実離れした謎のほうがいい。鉄道を巡って信じられないような事件が起こる。あり得ない、と驚く。でも、物語が進むにつれて、謎が論理的に解明されてゆく。そのギャップが大きければ大きいほど興奮できるのだ。
例えば、「幽霊列車」。本作は赤川次郎のデビュー作として知られている。走行中の列車から、乗客たちが消えてしまうのだ。
――ええ、人のいた(「いた」原文傍点)あとはありました。荷物は網棚に乗っかってるし、新聞がたたんで座席に置いてあるし、ふたを開けた、かんビールが窓ぎわに置いてありました。でも肝心のお客さんの姿が一人も見当りません。森君と二人で途方にくれてると、機関士の関谷君もやって来ました。で、三人で列車をくまなく捜しましたが、お客さんは一人もいない。(略)——ええ、全く見当もつきません、何があったのか。お客さん八人がみんな消えちまうなんて……(「お客さん~なんて」原文傍点)
出典:赤川次郎「幽霊列車」 『無人踏切』(光文社文庫、1986年)
史実として有名な帆船マリーセレスト号事件の列車版のような怪事件である。出来事の不思議さに対する謎の解明に加えて、動機の説得力も充分な名作だ。
この「幽霊列車」と併せて読みたいのが、連城三紀彦の「ゴースト・トレイン」である。タイトルからも窺がえるように、こちらは「幽霊列車」のパスティーシュとして書かれた一作だ。舞台背景や登場人物が被っているのだが、メインとなる謎はまったく異なるところが面白い。
「そのまま眠りに落ちたのか、気を失ったのか、気がついたら、うっすらと、白み始めた空が見えて、その線路の上にあお向けになって横たわっていた……列車が襲いかかってきた時と同じ姿勢でね」
出典:連城三紀彦「ゴースト・トレイン」 『連城三紀彦 レジェンド2』(講談社文庫、2017年)
線路に横たわった人間の上を、確かに通過したはずの列車が忽然と姿を消してしまったのである。「幽霊列車」は人間の消失、それに対して「ゴースト・トレイン」は列車の消失、この対比がスリリングだ。いずれの物語も、舞台となる鉄道路線がローカル線というところもポイントになっている。
最後に、「幽霊列車」「ゴースト・トレイン」に通じるタイトルを持つ詩を一つ紹介したい。石原吉郎の「葬式列車」である。似ているのはタイトルだけではない。本作は一つのミステリーとして読むこともできると思う。
なんという駅を出発して来たのか
もう誰もおぼえていない
ただ いつも右側は真昼で
左側は真夜中のふしぎな国を
汽車ははしりつづけている
駅に着くごとに かならず
赤いランプが窓をのぞき
よごれた義足やぼろ靴といっしょに
まっ黒なかたまりが
投げこまれる
そいつはみんな生きており
汽車が走っているときでも
みんなずっと生きているのだが
それでいて汽車のなかは
どこでも屍臭がたちこめている
(略)
ああそこにはたしかに俺もいる
うらめしげに窓によりかかりながら
ときどきどっちかが
くさった林檎をかじり出す
俺だの 俺の亡霊だの
俺たちはそうしてしょっちゅう
自分の亡霊とかさなりあったり
はなれたりしながら
やりきれない遠い未来に
汽車が着くのを待っている
誰が機関車にいるのだ
巨きな黒い鉄橋をわたるたびに
どろどろと橋桁が鳴り
たくさんの亡霊がひょっと
食う手をやすめる
思い出そうとしているのだ
なんという駅を出発して来たのかを
出典:石原吉郎「葬式列車」 『サンチョパンサの帰郷』(思潮社ライブラリー、2016年)
この不思議な詩の背景には、作者のシベリア抑留体験がある。汽車に詰め込まれて収容所へ送られてゆく亡霊めいた「俺」たちの姿。「いつも右側は真昼で/左側は真夜中のふしぎな国」とは、時差を含むような広大な大陸を感じさせつつ、より根源的には生と死が隣り合わせの場所のイメージだろう。ミステリーと詩には一つの共通点がある。それはどちらも魅力的な謎を孕んでいるということだ。





