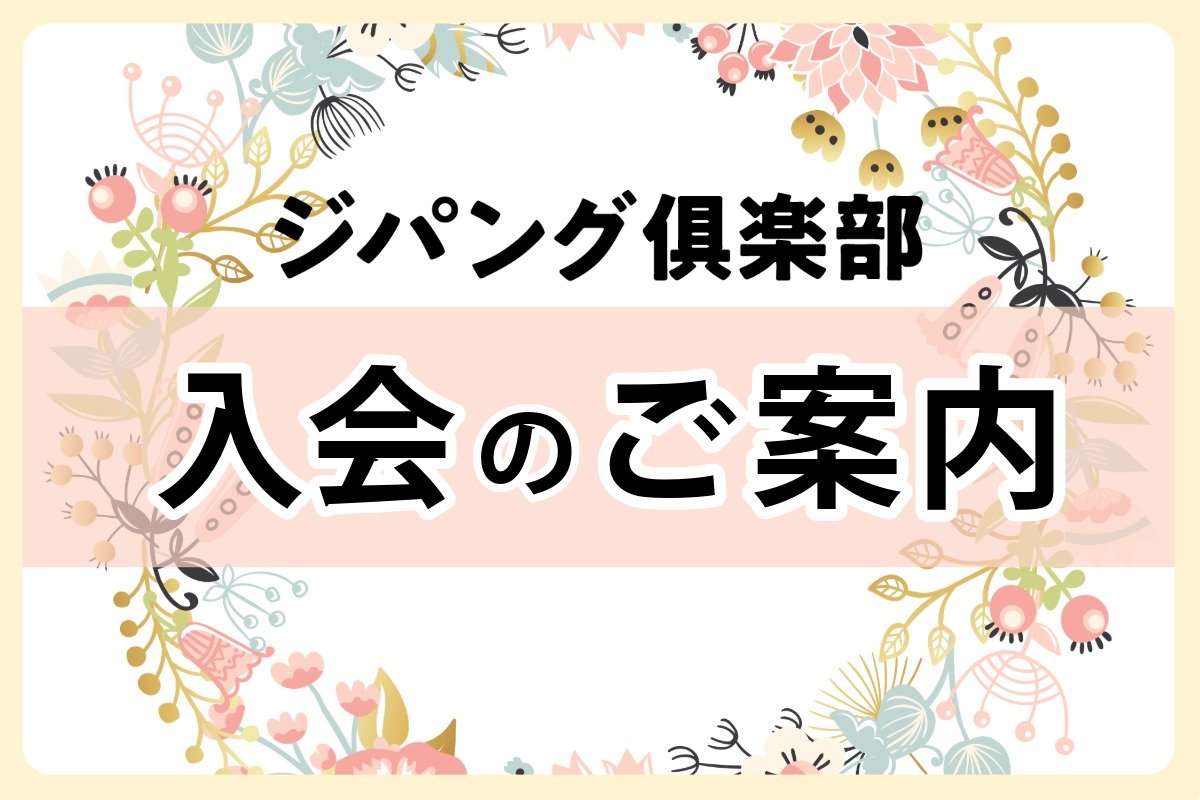2025.08.25ジパング俱楽部付知峡の渓谷紅葉と中山道中津川宿をめぐる|モデルコース

岐阜県中津川市
気候もよくなる秋の旅行シーズン。何世代も前から多くの人がその美しさに魅了されてきた歴史ある紅葉名所を歩く旅はいかがでしょう。列車やバスでアクセスしやすい秋の日本を歩くコースを紹介します。
中津川市北部の山あい、清流と紅葉が織りなす絶景が満喫できる付知峡(つけちきょう)で秋の自然をたっぷり味わい、さらに、街道情緒あふれる中津川宿(なかつがわじゅく)も散策して、ぜいたくな一日を過ごしましょう。
「ジパング倶楽部」会員募集中
モデルコース概要
| 紅葉の見頃 | 10月下旬~11月上旬 |
|---|---|
| 歩行距離 | 約14.7キロ |
| 所要時間 | 約7時間45分 |
- ※記事の所要時間は、駅から駅までのバスの移動や観光や食事、休憩を含む時間の合計です。
中央本線中津川駅からスタート!

特急「しなの」は上り・下りとも全列車が停車します。今回乗車する付知峡方面行きバスのほか、中山道の宿場町・馬籠(まごめ)行きや、国史跡の苗木城跡方面行きのバスも駅前から発着しています。中津川を拠点に、付知峡や周辺の名所をめぐる1泊2日の旅行プランも組み立てても楽しいかも。駅に隣接する「中津川市にぎわいプラザ」には、岐阜県東部の多彩なおみやげが揃っているので、帰りに立ち寄ってみては。
付知峡倉屋温泉バス停
 日帰り温泉施設の敷地内にあるバス停
日帰り温泉施設の敷地内にあるバス停
中津川駅を発車したバスは、木曽川を渡り、支流の付知川に沿って、中津川市北部ののどかな山里を走っていきます。
40分ほど走ると、付知峡の玄関口に位置する付知の町に入り、南北約2キロにもおよぶ長い町並みを通り抜けたところで、付知峡倉屋温泉バス停に到着。ここから今回の散策を始めます。
護山(もりやま)神社
この地の山々を護る神
 森閑(しんかん)とした雰囲気の境内
森閑(しんかん)とした雰囲気の境内
付知峡に向かう前に、まずはバス停から近いこの神社に参拝し、道中安全を祈願していきましょう。
この地域は「裏木曽」と呼ばれ、徳川幕府が保護する豊富な木材資源の産出地として知られてきました。この神社はそんな木曽の山々の総鎮守で、幕府の命を受けた尾張藩により、江戸時代後期の天保年間に創建されました。
伊勢神宮ともかかわりが深く、式年遷宮(しきねんせんぐう)で新調される御樋代木(みひしろぎ=御神体を納める器の材)の一部は、裏木曽の山林で伐採され、この神社から出発します。
清浄な空気が流れる境内には、1934(昭和9)年の台風で折れた樹齢950年の巨大ヒノキの標本が展示されています。
護山神社
| 問い合わせ先 | 0573-82-4433 |
|---|---|
| 時間 | 参拝自由 |
| 交通アクセス | 中央本線中津川駅から加子母総合事務所行きほか北恵那交通バス約50分の付知峡倉屋温泉下車、徒歩約10分 |
| URL | http://www.moriyama-jinja.jp/ |
付知峡
橋から絶景が眺められる!
 攻橋から眺める紅葉
攻橋から眺める紅葉
護山神社からは、付知川右岸の県道486号を歩いて付知峡を目指します。神社から4kmほどは、アップダウンのほとんどない平坦な道。のんびりした農村風景の中を進みます。
途中で坂道を下ってゆくと、やがて付知川に架かる攻橋を渡ります。この橋のあたりから上流部の広い範囲が「付知峡」と呼ばれています。攻橋は眺望ポイントのひとつ。橋から紅葉に包まれた深い谷を見下ろすことができます。
この先は約1キロ、2回のつづら折れを挟んだ坂道。ここもさほどの急坂ではありません。登りきってそのまま進むと、やがて不動公園に辿り着きます。
付知峡(攻橋付近)
| 問い合わせ先 | 0573-82-4737(付知町観光協会) |
|---|---|
| 時間 | 見学自由 |
| 交通アクセス | 中央本線中津川駅から加子母総合事務所行きほか北恵那交通バス約50分の付知峡倉屋温泉下車、徒歩約1時間 |
| URL | https://www.tsukechi.jp/ |
不動公園
心地よい滝のミストを浴びて
 不動公園の紅葉
不動公園の紅葉
 公園入口にある食事処
公園入口にある食事処
 カモシカに出くわすことも!?
カモシカに出くわすことも!?
 岩肌を流れ落ちる観音滝
岩肌を流れ落ちる観音滝
 渓谷を渡る吊り橋
渓谷を渡る吊り橋
道の終点には、付知峡の注目スポットである不動滝と観音滝があります。この2つの滝と渓谷をめぐる散策コースが整備されているのが不動公園です。
食事処の横のゲートをくぐると、そこはもう大自然の中。木立の中に続く歩きやすい歩道を進み、途中で階段を下りていくと、ドドドドという重低音とともに観音滝が姿を現します。そして、観音滝からもう少し下がって谷底を見下ろすと、そこには狭い谷を勢いよく流れ落ちる不動滝が。2つの滝の迫力に、しばし足を止めて見入ってしまうことでしょう。
散策路はのんびり歩いて一周40分ほど。弁当を持参していなかったら、入口の食事処でランチを。流しそうめんや「鶏(けい)ちゃん」が名物です。
不動公園
| 問い合わせ先 | 0573-82-4737(付知町観光協会) |
|---|---|
| 時間 | 見学自由 |
| 交通アクセス | 中央本線中津川駅から加子母総合事務所行きほか北恵那交通バス約50分の付知峡倉屋温泉下車、徒歩約1時間30分 |
| URL | https://www.tsukechi.jp/ |
付知峡倉屋温泉バス停
付知峡からの帰路は、行きとは違うルートをとり、途中までは付知川の左岸を歩きます。
中津川駅へのバスは、行きに下りた付知峡倉屋温泉バス停から乗車。このバス停は「付知峡倉屋温泉 おんぽいの湯」の敷地内に設けられています。もし、バスの時間まで余裕があれば、温泉に浸かって汗を流していくのもいいでしょう(第4水曜休、入泉料800円)。
中山道(なかせんどう)中津川宿
街道のにぎわいの面影が残る町
 老舗酒蔵が店を構える下町
老舗酒蔵が店を構える下町
中津川駅に戻ったら、帰りの列車に乗る前にもうひと歩き。駅前通りを300メートルほど進んだところで交わる旧中山道を辿って、中津川宿の中心部まで行ってみましょう。
商店街を抜け、四ツ目川を渡って「本町」に入ると、宿場町風情が色濃く残る家並になります。中津川宿は江戸から数えて45番目の宿場町。「中町」「横町」「下町」と続く家並は、うだつを上げた商家建築が点在しています。「うだつ」は隣家との境界に設けた防火壁のこと。富の象徴でもあり、中津川宿の繁栄ぶりが伺えます。
このほか、街道の防備のためわざと道を屈曲させた「枡形(ますがた)」も見どころです。
 中町から江戸方向を眺める
中町から江戸方向を眺める
中山道中津川宿
| 問い合わせ先 | 0573-62-2277(中津川市観光案内所) |
|---|---|
| 時間 | 散策自由 |
| 交通アクセス | 中央本線中津川駅から徒歩約12分(御菓子所 川上屋 本店付近まで) |
| URL | https://nakatsugawa.town/spot/%E4%B8%AD%E6%B4%A5%E5%B7%9D%E5%AE%BF/ |
御菓子所 川上屋 本店
名物・栗きんとんは外せない
 秋のみ販売の「栗きんとん」1個291円
秋のみ販売の「栗きんとん」1個291円
 「栗菓子」の看板に引き寄せられます
「栗菓子」の看板に引き寄せられます
 栗きんとんをようかんで包んだ「さゝめさゝ栗」1944円
栗きんとんをようかんで包んだ「さゝめさゝ栗」1944円
 落ち着いた店内でゆっくりおみやげ選び
落ち着いた店内でゆっくりおみやげ選び
中津川の名物として真っ先に名前が挙がるのが栗きんとん。折しも栗のシーズン真っ盛り。旅の最後は栗きんとんで締めくくりましょう。
中津川には和菓子店が多くありますが、なかでも中津川宿のほぼ真ん中あたりに店を構えるこちらは、幕末の1864(元治元)年創業という、中津川きっての老舗(しにせ)として有名です。
9月から12月のみ販売される定番の栗きんとんは、厳選した素材で丁寧に作り込んだひと品。口の中で栗が溶けるようにほどけ、やさしい甘みがいっぱいに広がります。
ほかにも、栗きんとんや栗を使った魅力的な和菓子を多数揃えており、おみやげ探しにもぴったりの店です。
御菓子所 川上屋 本店
| 問い合わせ先 | 0573-65-2072 |
|---|---|
| 時間 | 8時~19時30分 |
| 定休日 | 水曜 |
| 交通アクセス | 中津川駅から徒歩約12分 |
| URL | https://www.kawakamiya.co.jp/ |
中津川駅ゴール!
コースルート付き!紹介スポット一覧マップ
- ※マップのルートは山道の紹介を含むため、詳細な位置関係は実際と異なります。概要図としてご覧ください。
文・写真/内藤昌康
- ※記事中の情報は2025年8月時点のものです。
- ※列車やバスなどの所要時間は目安となる平均時間を表記しています。バスの運行本数が少ない場合がございますので、事前にご確認ください。
- ※花や紅葉など季節の景観は、その年の天候などにより変動しますので、現地へご確認ください。
- ※店や施設のデータは、原則として一般料金(税込)、定休日、最終受付時間・ラストオーダーを、宿泊施設の料金は平日に2名で宿泊した場合の1名分の料金(1泊2食・税・サービス料込み)を記載しています。
- ※同一商品で軽減税率により料金の変わるものは、軽減税率が適用されない料金を記載。臨時休業などは省略しています。また、振替休日なども祝日として表記しています。