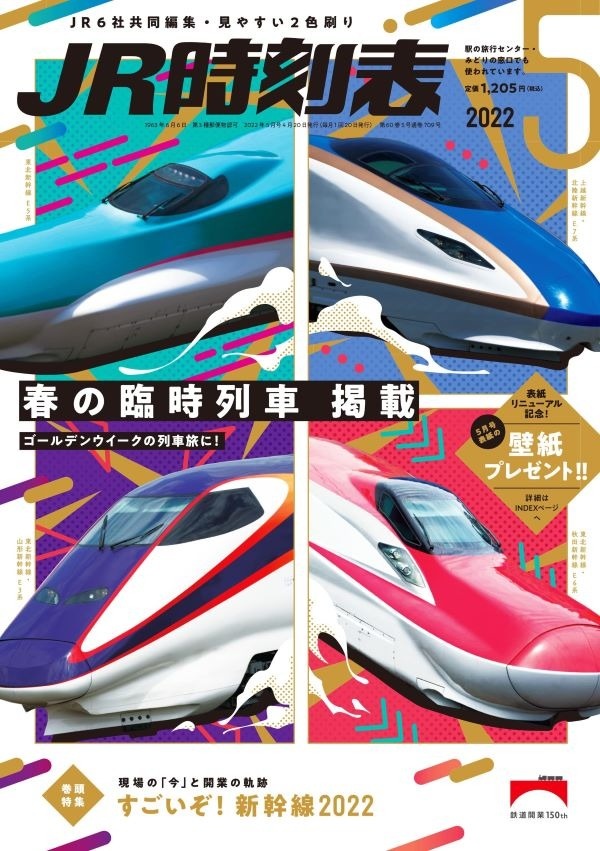東海道新幹線の安全運行を日々支える「浜松工場」の仕事とは
速達タイプの新幹線としてなじみのある〔のぞみ〕が、2022年3月に誕生30周年を迎えました。東海道新幹線の安全運行を支える浜松工場では、いわば新幹線の健康診断が行われています。日々どのような検査や修繕が行われているのか、この工場で働く技術者のお二人に話を伺いました。
新幹線車両を隅々まで検査・修繕する専門工場
東海道新幹線の下り列車に乗って浜松駅を過ぎると、進行方向右側に「JR東海」と書かれたきれいな建物が見えてきます。それが、JR東海の浜松工場。東海道新幹線の車両の検査・修繕を行う施設です。1912(大正元)年に蒸気機関車の修繕工場として創設され、2011(平成23)年からは新幹線車両専用の工場となりました。長年にわたって増改築を繰り返し検査工程が複雑化していましたが、2017(平成29)年に新建屋が完成し、検査工程が最適化されました。現在はJR東海と協力会社を合わせて約1400人が日々働いています。
新幹線の車両には、4種類の定期検査があります。なかでも浜松工場で行われているのは、最も大がかりな「全般検査」。前回の全般検査から3年以内、または120万kmを走行するまでに実施され、部品レベルまで分解して検査・修繕を行います(一部の車両を除き4月以降、3年4カ月以内または160万kmを走行するまでに順次検査周期を延伸)。台車や床下機器、座席といった構成物をすべて解体し、それぞれ専用の検修場で検査・修繕を実施します。1編成16両の全般検査は14日間かけて行われ、年間約50編成を検査します。
 1両ずつに分割された車両は隣の車体解体場へ
1両ずつに分割された車両は隣の車体解体場へ
 工場間の移動には左右に動くトラバーサーを使用する
工場間の移動には左右に動くトラバーサーを使用する
工場に入場した編成は、まず4両ごとに分割されて、パンタグラフやドアなどの装備品が外されます。さらに1両ごとに分けられて車体解体場に送られ、車体と台車を分離。床下の機器類もすべて解体されます。車体は隣の車体加修場で修繕を受け、一方機器類は部品検修棟で機器ごとに検査・修繕を受けます。
鏡を駆使して台車をくまなくチェック 台車センター・野間口芽生(のまぐち めい)さんの仕事

第一部品検修棟1階の台車センターには、専用の台車検修ラインがあります。車体から分離された台車は、ここでさらに台車枠と車軸(左右に車輪がついた軸)に分離され、それぞれ検査・修繕を受けます。再び台車が組み立てられると、台車走行試験へ。専用の台車走行試験装置で毎回300km/h以上の走行状態を再現し、異音や異常振動はないか、各部の温度は適正であるかを約1時間かけて確認します。
 走行時と同じ環境を再現する台車走行試験機
走行時と同じ環境を再現する台車走行試験機
 東海道・山陽新幹線の最高速度は300km/h(山陽新幹線区間)。台車走行試験は、それを上回る速度で実施される
東海道・山陽新幹線の最高速度は300km/h(山陽新幹線区間)。台車走行試験は、それを上回る速度で実施される
台車走行班として、ここで台車の確認作業を担当しているのが、入社3年目の野間口芽生さん(22)です。
「試験中は、振動と温度をモニタリングしています。表示される数値を見るだけでなく、試験室から伝わってくる音や振動に異常がないか、五感を使って品質を確認しています」
試験が終了すると、今度は実際に目視での確認を行います。
「ピット内に入ったり、手鏡とライトを使ったりして、微妙な油にじみがないか、『踏面(とうめん)』といって車輪がレールに接する部分に傷がないかなど、台車の隅々までチェックします」
 大勢の方が新幹線を利用していることに驚いたという野間口さん。「新幹線は日常的に使われる大切な交通機関なので、少しでも良いものを提供したい」と語る
大勢の方が新幹線を利用していることに驚いたという野間口さん。「新幹線は日常的に使われる大切な交通機関なので、少しでも良いものを提供したい」と語る
野間口さんは、鹿児島県出身。高等専門学校で機械・情報プログラミングを専攻していました。
「インターンシップで新大阪に来た時、新幹線に関わる仕事を見て格好いいなって憧れたことが就職のきっかけです。出身地の鹿児島で過ごしていたころ、私にとって新幹線は旅行のときに乗るものだったのですが、東海道新幹線は通勤に使っている人も多くて、日常に欠かせない存在なんだと思いました」
 台車の裏側までくまなくチェックするには、特殊な鏡やライトが欠かせない
台車の裏側までくまなくチェックするには、特殊な鏡やライトが欠かせない
高専卒業後、JR東海に就職。研修期間を経て、浜松工場の台車センターに配属されました。
「最初のうちは、測定器の取り付けも難しく大変でした。台車はレールと車体をつなげる重要な部分ですから、調べれば調べるほど、いろいろなことが見えてきます。とても難しい作業ですが、小さな油にじみや傷をしっかりと見つけることができると、頑張ったなって思います」
作業は、4人1組の班単位で行います。入社から日が浅い野間口さんは、毎日が勉強。
「私以外は男性の先輩です。班長は、すぐに『ありがとう』と声をかけてくださる尊敬できる人です。率先して動いてくれるリーダーで、私も頑張ろうって思います」
班をまとめ、車体を正確に組み上げる 車体センター・村松大輔(むらまつ だいすけ)さんの仕事

さて、各種検査・修繕が完了した車体は、ロボットによる塗装作業を経て、車体センターの「車体ぎ装場」へやって来ます。検修を終えた各種機器類も集められ、ここで車体への取り付け作業が行われます。
この作業を行う車体機器ぎ装班の班長を務めているのが、入社16年目となる村松大輔さん(33)です。静岡県磐田市出身で、高校卒業後に就職。初代〔のぞみ〕である300系をはじめ、2020年に東海道新幹線から引退した700系、現在主流のN700Aなど、歴代車両の検修を担当。2007(平成19)年に登場したN700系へ、N700Aに採用されている機能の一部を取り込む改造工事を担当したこともあるなど、東海道新幹線の車両を知り尽くした若きベテランです。
 検査・修繕を終えた床下機器をひとつひとつ丁寧に取り付ける
検査・修繕を終えた床下機器をひとつひとつ丁寧に取り付ける
「大勢の人の役に立つ仕事がしたいと思って、就職しました。今は、検査が完了した床下の大型機器を車体に取り付けて、電線や配管を接続したり、エアの漏れを確認したりする作業を行っています。9人の班で決められた時間内に1両を仕上げるので、チームワークが大切です」
車体機器ぎ装班に限らず、浜松工場での作業は、原則として1工程105分(一部210分)で行います。これは1日の作業時間である7時間(420分)を4分割したもの。この時間内に主変換装置や空調などの大型機器を確実に取り付け、確認するのです。
「9人で作業を分担し、時間内にしっかり作業を完了して次の工程へ車両を送れた時に、充実感を覚えます」
一口に「床下機器」といっても、その種類はさまざま。車両ごとに取り付ける機器も異なります。使用する工具も機器によって変わるので、複数のトレイを用意し、機器ごとに必要な工具をまとめておく工夫がなされています。
 機器により使用工具が異なるため、機器ごとにトレイを分けている
機器により使用工具が異なるため、機器ごとにトレイを分けている
 トレイ内の工具の定位置が決められているなど、徹底した管理を実施
トレイ内の工具の定位置が決められているなど、徹底した管理を実施
「休みの日にもDIYでキャンプテーブルなどを作っていて、物作りが元々好きなんです。なので、新幹線の車両を組み立てる仕事は楽しいです」
そう語る村松さんは、車体機器ぎ装班の班長になって2年。自分の技術を磨くだけでなく、班をまとめていくのも大切な仕事です。
 「自分にとって一番誇れるものが新幹線」と語る村松さん。乗客として利用するときも、特に自分が改造を担当したN700Aを見かけると愛着を感じるそう
「自分にとって一番誇れるものが新幹線」と語る村松さん。乗客として利用するときも、特に自分が改造を担当したN700Aを見かけると愛着を感じるそう
「決められた作業を行うだけでなく、訓練プログラムを自発的に考えて、班員の教育を実施しています。作業にあたっては指示を出すばかりでなく、自分が先頭に立って動くように心がけています」
検査・修繕を終え、再び営業運転へ
元通りに組み立てられた車体は、台車を装着した後、出場検査へ。新車同然の美しい姿となった車両は再び16両に組成され、浜松〜名古屋間での試運転を行った後、出場(営業運転へ復帰)します。
 リフティングジャッキを用いて、車体と台車を繋ぎ合わせる
リフティングジャッキを用いて、車体と台車を繋ぎ合わせる
 試運転を終えた車両が、工場の手前にある東海道新幹線唯一の踏切を通る
試運転を終えた車両が、工場の手前にある東海道新幹線唯一の踏切を通る
「班長を見習って、後輩に頼られたり、助けてあげたりできるような技術者になりたいです」(野間口さん)
「車体機器ぎ装はもちろん、車両などの改造工事についても一層技術を磨き、後世に継承していきたいです」(村松さん)
世界トップクラスの安全性を誇る東海道新幹線。その車両の安全は、村松さんや野間口さんのような技術者の地道な作業によって保たれているのです。
著者紹介
新幹線の現場の「今」と開業の軌跡は、『JR時刻表』2022年5月号で!
『JR時刻表』2022年5月号では、「すごいぞ! 新幹線2022」と題し、ここでご紹介した「JR東海 浜松工場」のほか、新幹線に乗務する運転士・車掌が所属する「JR東日本 東京新幹線運輸区」を取材! また、新幹線の車内サービスの変遷も紹介しています。ぜひご覧ください!
JR時刻表2022年5月号
- ※取材・撮影=栗原 景
- ※掲載されているデータは2022年4月1日現在のものです。