2023.08.25鉄道新幹線の自動放送は「行き先案内人」 アナウンサー 堺 正幸さんスペシャルインタビュー
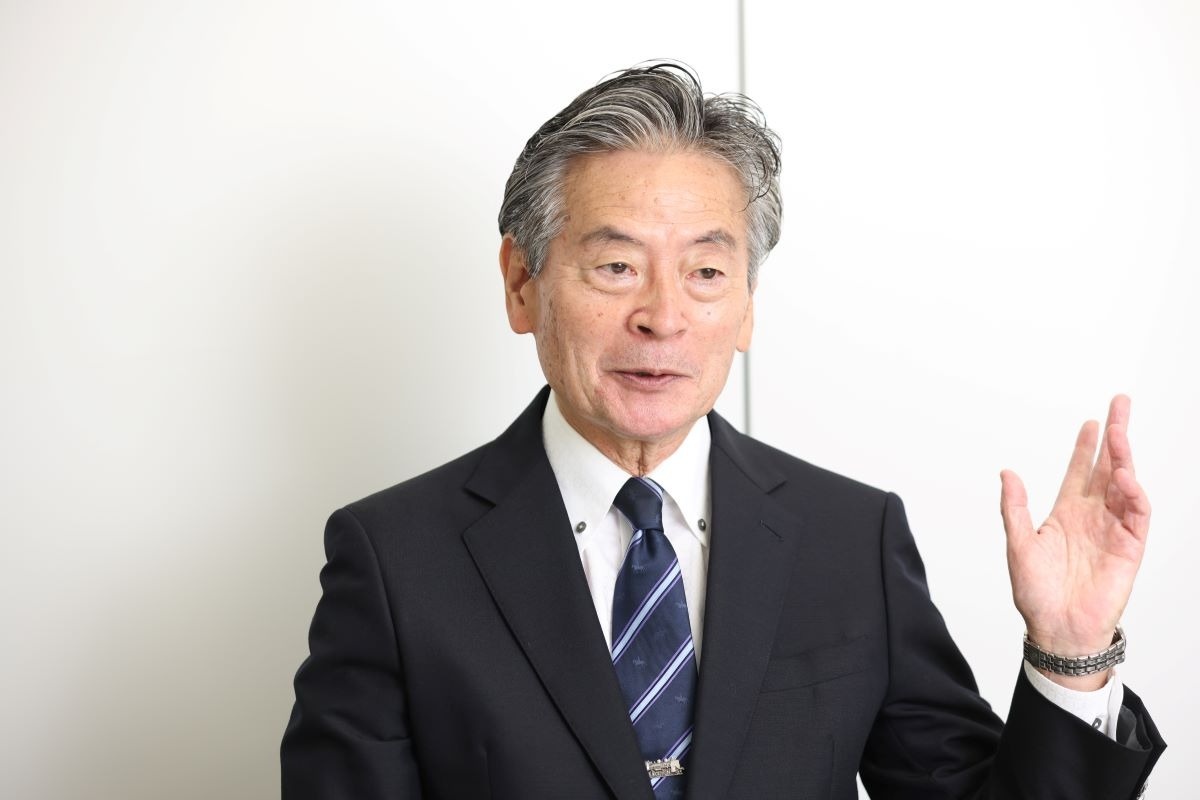
自動放送の声に乗せた思いや録音秘話を語る
『JR時刻表』2023年9月号(8月25日発売)巻頭特集「ようこそ車内放送の世界へ」で、JR北海道・JR東日本の新幹線、JR東日本の特急列車の車内放送(自動放送)を担当するアナウンサー 堺 正幸さんに話を伺いました。インタビューのフルバージョンをお届けします。
『JR時刻表』×トレたび 連動企画です。
旅に寄り添うあの声は、どのように誕生したのか
車内放送は美声すぎるのもよくないと言われました
私が初めて担当した車内放送は、フジテレビ入社7年目の29歳の時で、翌年の1982(昭和57)年6月開業の東北新幹線(大宮~盛岡間)、11月開業の上越新幹線(大宮~新潟間)でした。
国鉄(当時)の担当者から、たまたまフジテレビに「両新幹線に導入する自動車内放送をアナウンサーに頼めないか」という打診があったそうです。当時のアナウンス部のデスクは私が鉄道好きだと知っていたので声をかけてくれました。以来、延伸や開業のたびに車内放送のご依頼をいただき、42年間続けさせていただいています。
なぜそんな長きにわたり担当させてもらえているのか、それは私にもわかりません。ただ、車内放送は美声すぎるのもよくないと、以前、どなたかに言われたことがあります。あまりにもいい声だとうっとりと聞き入ってしまって、「あれ? 次どこだっけ? 」となりかねないですもんね。ですから、基本的には右耳から入って左耳にすっと抜ける。でも、駅名などの情報が耳に残ることが大事だ、と。何よりご縁があったんでしょうね。
ところで、人の声は日によって微妙に違うんですよね。年齢によっても変わりますし。最近録音した北陸新幹線の金沢~敦賀間(2023年度末開業予定)の延伸分は、前回の録音から9年近くも経っている。ですから、録音当日は必ず前回の音声を聞かせてもらい、声のトーンなどを確認してからそれに合わせるように録音しています。先日、特急〔成田エクスプレス〕に乗車した時、自分の声の車内放送を耳にしたのですが、「これいつの録音だったかな? 声が若いな」って自分でわかるんですよね。
初めて自分の声を車内で聞いたのは、当時担当していた競馬中継の仕事で乗った東北新幹線でした。最初はくすぐったい妙な感じがしましたが、何回か聞くうちにすぐ慣れて、それこそ、右から左へ抜けるようになりました。ただ、当時のアナウンス部の部下たちの反応はまた別で、「プライベートなのに車内で堺さん(当時のデスク担当)の声が聞こえると、どこまでついてくるんだろう……って思ってしまうんです」とよく言われました(笑)。

録音前に気を遣うのは、風邪をひかず、カラオケに行かないことかな(笑)
競馬やスポーツ中継のアナウンスは盛り上がってくると、ちょっと絶叫調で早口になりがちです。私自身もどちらかといえば早口なので、車内放送の原稿を読む時のスピードは、あえてゆっくり読むことを心がけています。
また、日本語で最も大切なのは何といっても語尾。アナウンス技術の基本でもありますが、尻すぼみにはせず、語尾までしっかり同じ音量を出しきることが大切です。車内には若い人もお年寄りも、いろいろな方が乗っていますから、誰にでも聞きやすくないといけないと思うのです。
それから、車内放送の録音で一番難しいのは駅名のアクセント。たとえば、関東だと「熊谷」、上越新幹線の「浦佐」、北陸新幹線の「飯山」などでしょうか。現地では微妙にアクセントが違うこともあるので、録音には現地JRの担当者が立ち会ってチェックをしてもらいます。
あと気を遣うのは、録音の前に風邪をひかないこととカラオケに行かないことかな(笑)。ちなみに、カラオケでは狩人の『あずさ2号』が好きでよく歌っていました。
国鉄からJRになって、車内放送の文言が変化しました
車内放送の録音で印象に残っているのは、やっぱり最初の録音ですね。東京都文京区の護国寺駅近くにあった本当に小さなスタジオブースだったことをよく覚えています。当時はまだオープンリール(当時主流だった磁気テープ)で録音をしていたんですよ。
1回の録音時間は長いときで3~4時間。最近はこれまで録音した音声を使うことから、原稿枚数が少なくなったので、録音時間も短くなりました。録音機材も進化して、デジタル録音になった今は再録音も簡単になって、語尾やイントネーションなどがおかしい時や、少しでも気になったら自己申告して、自分が納得いくまでやらせてもらっています。
国鉄からJRになってからは車内放送にも変化がありました。特に変わったのは文言。それまではなかった「本日も東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます」のように感謝の言葉が加わったんです。
そうそう、録音でいえば、列車の号数のとり方も独特かもしれません。
まず、「1号、2号……10号」と10まで「号」を付けて読みます。その後、二桁の「10、20、30……90」、三桁の「100、200、300……900」まで読みます。それらを後は編集で合成するんです。965号なら「900」「60」「5号」を組み合わせる。ですから、テープ時代の放送を聞くと“間”がありますが、デジタル時代の今はぎゅっと“間”を詰められるので、よほどじっくり聞かないと、言葉の継ぎ目はわからないと思います。
車内にはいろいろな目的の人が乗っているわけですよね。楽しい旅だけじゃなくて、不幸があって故郷に戻らないといけない人もいる。そういう乗客のみなさんに、次の駅、乗り換えなどの情報を正確に届けるお手伝いをしているつもりでいるんです。ですから、ニュース原稿と同じように、あまり抑揚はつけずにフラットに読むことを大切に、毎回取り組んでいます。言うなればこの仕事は、「行き先案内人」でしょうか。

海沿いを走る列車が好きで、晴れると海が見たくなるんです
私は鉄道が好きなので列車に乗るのも大好き。運転席の後ろなら何時間でも立っていられます。
座席指定ができる列車なら海側を選びますね。海沿いを走る列車が好きで、晴れていると海が見たくなるんです。朝起きて天気予報で「今日は快晴です」と聞いて用事がなければ、「ちょっと根府川(ねぶかわ)に行ってくるね」って。根府川の海は本当にきれいなんですよ。訪れる時は必ず缶ビールを持って、ザザーッと波の音を聴きながらしばらくたたずんでいます。
もっと時間がある時は、東京駅から特急〔わかしお〕に乗って安房鴨川へ。内房線で浜金谷駅まで行くと、金谷港から東京湾フェリーに乗っちゃうんですよ。
 何度訪れても美しい根府川の海は、こどもの頃からのお気に入り(写真=交通新聞クリエイト)
何度訪れても美しい根府川の海は、こどもの頃からのお気に入り(写真=交通新聞クリエイト)
まだJRの全路線制覇はしていませんが、海沿いを走る路線を含めて乗っていない路線はできる限り早く乗りたいなと思っています。お子さんたちにはぜひSLに乗ってもらいたい。動態保存されている蒸気機関車は、普通の電車とは別物なんですよね。電車はスッと動いて加速するけど、蒸気機関車はゆっくりとスタートして加速していく。それに合わせて先頭から連結器がガチャガチャと音が鳴ってきて自分のいる客車にも伝わる。さらに煙のにおいも体感してほしいですね。
ベテランの鉄道好きな方はすでにいろいろな鉄道旅をされているでしょうから、その経験はもう財産です。上野発の蒸気機関車なんて経験したくてもできないですよ。今はエアコン完備で車内環境は快適ですが、窓を開ければその土地の匂いが入ってくる。そんなふうに五感で鉄道を感じられることって貴重ですよね。
ですから、これはしょうがないことですけれど、乗車してすぐ寝ちゃう人とか、せっかく窓際に座っているのに景色を見ない人がいると、「もったいないなあ」ってついつい思ってしまうんですよ。
堺 正幸(さかい まさゆき)
1952年、神奈川県川崎市生まれ。元フジテレビアナウンサー。『FNNスピーク』『スーパー競馬』『みんなの鉄道』など数々の番組に出演。現在もナレーションなど幅広い分野で活躍している。
著者紹介
『JR時刻表』2023年9月号 巻頭特集「ようこそ車内放送の世界へ」もあわせてチェック!
JR時刻表2023年9月号
- ※取材・構成=下里康子、撮影(特記以外)=鈴木愛子
- ※掲載されているデータは2023年8月1日現在のものです。


