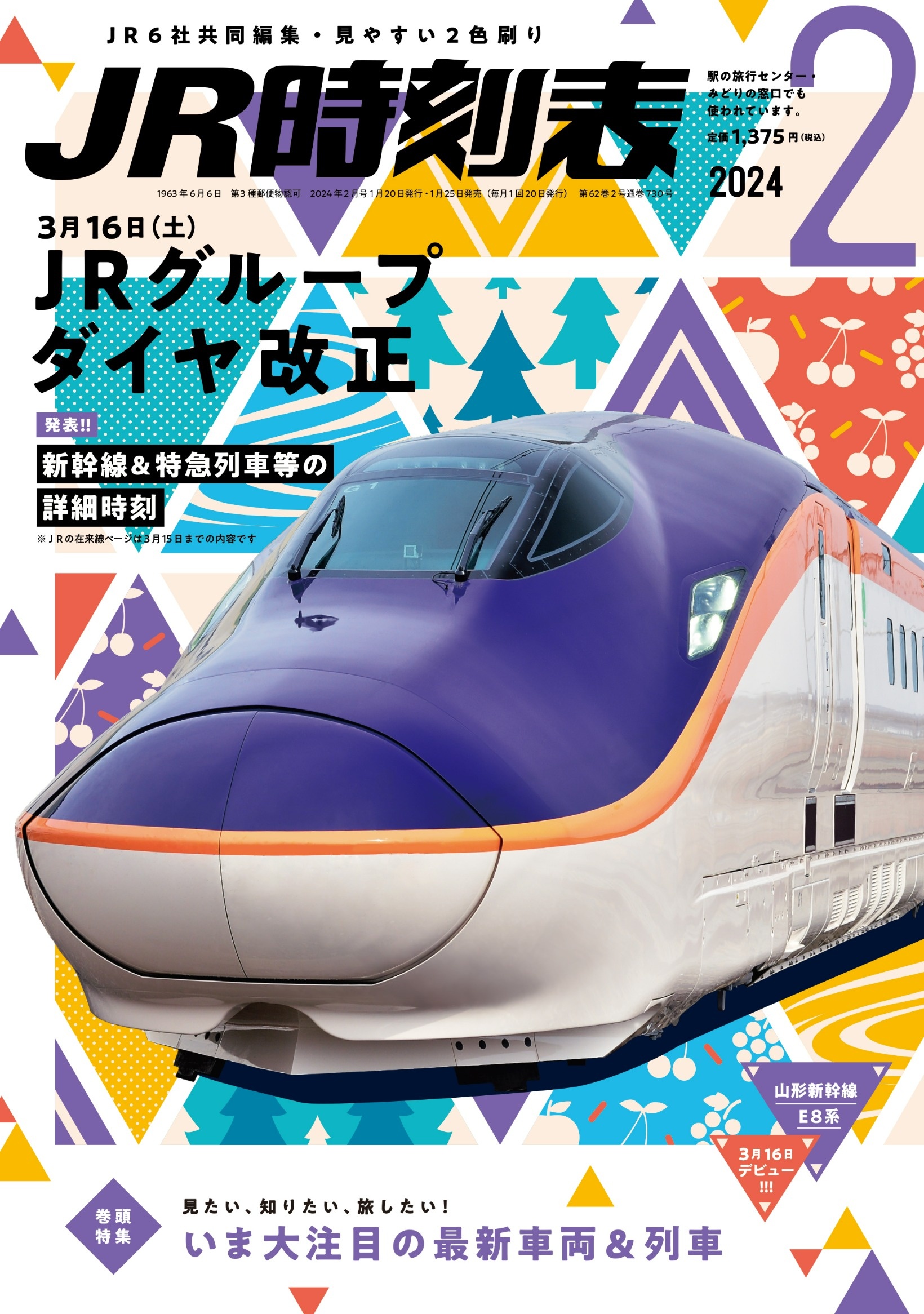JR九州に聞いてみました!
『JR時刻表』編集部がJR各社に鉄道にまつわるさまざまな疑問をQ&A方式で聞いていく連載です。
今回は……
Q. 在来線運転士の仕事について教えて!
在来線運転士の勤務形態や仕事のやりがいについて、JR九州(博多運転区・長友主任運転士)に聞いてみました!
A. 安全を第一に、日々乗務・訓練に臨んでいます
運転士になるために必要な免許・研修
運転士になるためには、駅員や車掌などを経験したあとに、まず社内試験を受けます。合格後に養成所で机上研修、運転職場(運転区)で実務研修を受け、「動力車操縦者運転免許」という国家資格を取得後、晴れて運転士になることができます。JR九州には約1300名の在来線運転士が在籍し、女性は4%ほどです。
泊まり勤務で昼夜の運行を支える
運転士の代表的な勤務スケジュールは、出社後、制服に着替え、アルコールチェック・点呼を受け、普通列車や特急列車への乗務を開始。その日の終着駅に泊まり、2日間で24時間程度の勤務を行います。
お客さまの安全を第一に乗務するために、時間や体調の管理はもちろん、休日の過ごし方も日々大切にしています。
欠かせない仕事道具は、時刻表や規程類・運転支援アプリなどの入る業務用タブレット、マスコンキー(運転時に使用)・忍び錠(乗務員室に入る際に使用)などの鍵類です。担当する車両によってはブレーキハンドルも必要です。
 乗務に必要な業務用タブレット・錠束・ブレーキハンドル
乗務に必要な業務用タブレット・錠束・ブレーキハンドル
お客さまに安心してご利用いただくための研鑽も
また、運転士は毎月2時間ほど、訓練や勉強会に参加しています。ヒューマンエラーに対する事例研究、規程や設備の変更点など机上で学ぶものだけでなく、実際の車両を使用した避難誘導、接客のロールプレイングやお手伝いが必要なお客さまの応対訓練なども行っています。
運転業務以外でも、さまざまな資格を取得するために社外通信教育に取り組む運転士も増えています。
日々の乗務で意識する「乗り心地」
乗務では、安全第一であることはもちろん、どの列車も乗り心地にも気を遣っています。特急列車や観光列車は駅の通過も多く、車内でお食事をされているお客さまも大勢いらっしゃいます。
衝動防止のために、ノッチ(加速)やブレーキ扱いの回数を極力減らせるように、運転時刻や先を走る列車の状況を予測しながら計画的に運転操作を行っていますが、ブレーキ感覚を養うことには特に苦労しました。
ほかにも、常に最悪の事態を想定し、安全を意識して行動することや、同僚の経験した事象について「自分だったらどのように対応するか?」というシミュレーションを欠かしません。
 安全を第一に、憶測で行動しないことを日々大切にしている
安全を第一に、憶測で行動しないことを日々大切にしている
見習い運転士として乗務した日のこと
就職活動の際、「地元の九州で働きたい」という思いがあり、最初に思い浮かんだJR九州に就職しました。故郷は宮崎なのですが、JR九州のテレビCMを目にしていたことや、中学・高校時代に電車通学をしていたことも、動機に影響しているかもしれません。
見習い運転士として初めて乗務したときは、「あっ、本当に電車が動いた!」と素直に感じました。自分が運転をしているのに、まるで電車に動かされているような不思議な感覚を抱いたことを今でもよく覚えています。
私にとって身近なJR九州でしたが、乗務中にお客さまや沿線の方が手を振ってくれるときに、運転士としてとてもやりがいを感じます。
ぜひ見てほしい九州の絶景
九州各地には、たくさんの絶景スポットがあります。博多エリアを中心に乗務をしていますが、周囲に何もない駅に到着したときに、きれいな星空を見上げることが好きです。
そして、JR九州では皆さまに楽しんでいただけるような、さまざまなイベントや仕掛けをいつも考えています。九州の絶景や、わくわくするような体験をしに、ぜひ九州へお越しください。
 運転士の仕事について答えてくれたJR九州の長友主任運転士
運転士の仕事について答えてくれたJR九州の長友主任運転士
- ※『JR時刻表』2024年2月号掲載時点の内容です。
- ※画像=JR九州提供
- ※構成=時刻表編集部