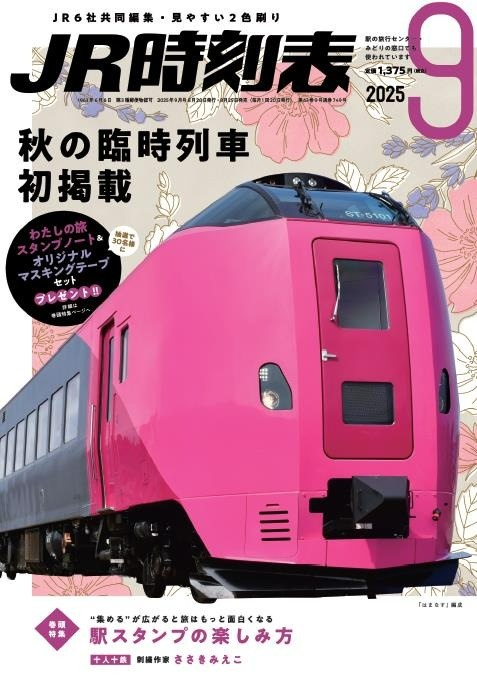東海道新幹線のリサイクルについて教えて!
『JR時刻表』編集部がJR各社に鉄道にまつわるさまざまな疑問をQ&A方式で聞いていく連載です。
今回は……
Q.東海道新幹線のリサイクルについて教えて!
東海道新幹線の車両が引退後、廃材としてどのように再利用されているのか、JR東海に聞いてみました!
A.引退した車両が、姿を変えて新たな価値を生み出しているんです。
引退した東海道新幹線から生成される再生アルミ
1999(平成11)年に運転を開始し「カモノハシ」の愛称で親しまれた東海道新幹線700系は、2020年に惜しまれつつもその役目を終えました。
 引退を記念した装飾が施された東海道新幹線700系
引退を記念した装飾が施された東海道新幹線700系
「引退した東海道新幹線が形を変え、2度目の人生をスタートさせる」というコンセプトのもと、東京2020オリンピックの開催にあわせてリニューアルを計画していた、東京ギフトパレット(東京駅八重洲北口改札外にあるギフトショップ)の外装(柱や天井など)への活用を目標に、リサイクル方法の研究を始めました。
東海道新幹線の車両には、何層にも重ねられた塗装や制振材、断熱材など、さまざまな付着物が施されています。特に、700系にはダブルスキン構造の中に断熱材などが組み込まれており、それ以外にもアルミ以外の物質からなる部品が内側に取り付けられているため、これらの分別は非常に手間のかかる作業でした。そのため、これまでは高純度のアルミ合金を抽出することが技術的に難しく、リサイクルといっても鉄の溶解時に用いる脱酸材など、限定的な用途にとどまっていました。
しかし今回のプロジェクトでは、JR東海グループが新幹線の車両に使用されていた廃材アルミから付着物を除去し、高純度のアルミ合金を抽出する手法を独自に開発。これにより、多様な製品への展開が可能な再生アルミの生成が実現しました。
 再生アルミ合金のビレット
再生アルミ合金のビレット
“良いことずくめ”の再生アルミ、その多彩な展開
新幹線車両に使用されているアルミは強度が高いため、そこから生成された再生アルミも高い強度を保持しており、装飾用途にとどまらず、建築材料や精密機器などにも幅広く活用されています。また、車両1両あたり約4トンもの再生アルミを生成することが可能です。さらに、再生アルミは、アルミを新製する場合に比べ、製造時に必要なエネルギーを抑えられるため、CO₂排出量を97%削減し、環境への負荷を軽減しています。
 東京ギフトパレットの外装
東京ギフトパレットの外装
 再生アルミを使用したアイスクリームスプーン
再生アルミを使用したアイスクリームスプーン
そんな“良いことずくめ”の再生アルミは、東京ギフトパレットの外装をはじめ、駅舎の外装や東海道新幹線N700S系の荷物棚など、建材として幅広く活用されています。さらに、ネクタイやスプーンといった雑貨から、子ども用の野球バットやエレキギターに至るまで、実に多彩なアイテムへと生まれ変わっています。
リサイクルを通じて環境負荷軽減の取り組みを推進するとともに、普段当たり前のように利用している身近なアルミ商品が「実は、もともとは新幹線だった!」というすてきな驚きを、皆さまへお届けできるよう 、これからも技術の向上に努めていきます。
- ※『JR時刻表』2025年9月号掲載時点の内容です。
- ※写真/JR東海、㈱SUS
- ※構成/時刻表編集部