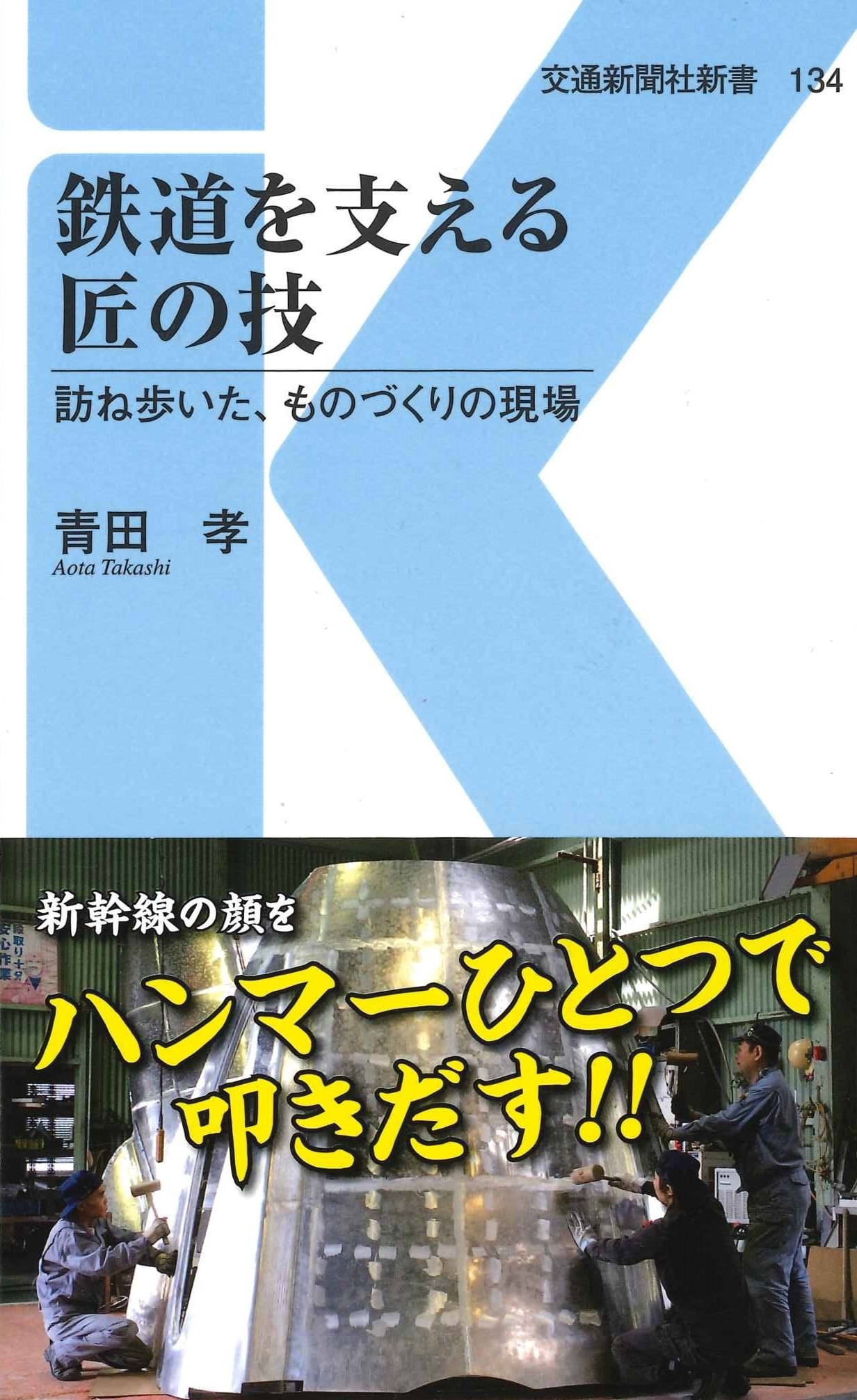安全で安定した運行を支える「ものづくり」の現場
鉄道の安全で安定した運行を支えているものといえば?
もちろん、いつもお世話になっている鉄道会社ですね。少し詳しい方なら、ナントカ製作所やホニャララ重工業といった車両メーカーも思い浮かべるしょう。
でも、それだけでは鉄道は動きません。車両を形づくる金属、座席を覆う織物、車両をつなぐナットなど多岐にわたる「もの」が鉄道を動かしているわけです。
そしてそれらの「ものづくり」は、誰もが知る大企業による技術によるものかと思いきや、おや、一般的にはあまり名を知られていない企業もそこここに。
交通新聞社新書『鉄道を支える匠の技』の著者で、鉄道業界誌『JRガゼット』にも執筆する青田 孝さんが訪ねた、キラリと光る企業の一部をここでご紹介します。
- ※写真はすべて交通新聞社新書『鉄道を支える匠の技』(2019年発行)掲載より。現在は写真と異なる場合があります
- ※トップの写真は、職人が新幹線の「おでこ」を成型している様子(写真:山下工業所提供)
「おでこ」を叩きだすのは、機械ではない
 職人が使い分ける各種ハンマー
職人が使い分ける各種ハンマー
まず青田さんが訪ねたのは、山口県下松市にある「山下工業所」。専門用語で「おでこ」と呼ばれる新幹線の先頭部分を「打ち出し板金」で叩きだしてきた企業です。
叩きだすのは機械ではなく、職人が手に持ったハンマー。ひたすら叩き、鉄やアルミ合金の板を伸び縮みさせ、複雑な曲線や三次元自由曲面をつくり出します。
鉄板を大まかに曲げたり、切断したりといった作業は機械に任せますが、重要な部位には職人の技術が欠かせません。
お尻の下、座席の張地にも光る匠の技
 モケット専門の織機
モケット専門の織機
座席の張地にも注目しましょう。
鉄道の張地は「モケット」と呼ばれる生地が一般的です。青田さんは、鉄道業界で常に5割以上のシェアを占めてきた大阪市の「住江織物」を訪ねました。
経糸と緯糸の組み合わせで織られた布から、芝が生えるように「パイル」と呼ばれる糸が起立したモケット。地になる布に直接触れることがないために、座席など過酷な使用条件のもとでも長持ちするほか、滑らかな肌触りも特徴です。
ゆるまないけど、ゆるめられる、不思議なナット
 レールの継ぎ目にも使われるナット
レールの継ぎ目にも使われるナット
何があってもゆるまないけど、ゆるめたいときには簡単にゆるめられるナットがありました。東大阪市にある「ハードロック工業」による、その名もハードロックナットです。
凸型と凹型、ふたつに分けたナットを組み合わせ、ボルトの中心方向に強力な応力を発生させるというこの技術は、橋梁、発電所、鉄塔、さらには人工衛星など多岐にわたる産業を支えています。
他業界も唸る「ものづくり」の技術
早期地震警報システム、精密な線路の分岐器、死角をなくすミラー……まだまだある鉄道を支える「ものづくり」。
それぞれが専門分野における世界的トップレベルの技術なわけですから、インターネットには書けない企業秘密もたくさんあります。
ご興味を持たれた方には、交通新聞社新書『鉄道を支える匠の技』をおすすめします。
運輸・交通業界および関連業界にとどまらず、他業界も唸る20社の「匠の技」がつまった1冊です。