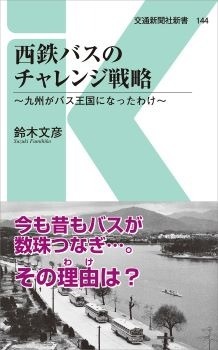バス王国・九州の中枢を担う西鉄バスとは?
福岡県の博多駅前や天神交差点に立つと、目の前を絶え間なくバスが往来している光景に出会います。実は九州は「バス王国」とも呼ばれるほどで、近距離、遠距離を問わず、バスを利用する人が多いのです。その中心にある西鉄バスの実際を、『西鉄バスのチャレンジ戦略』(交通新聞社新書)より一部抜粋してご紹介しましょう。
- ※トップ写真は、西鉄バス「由布院とよくに号」。九州では高速道路網が整備される前から路線バスが発達していた
「ムーンライト号」の衝撃
 「ムーンライト号」の2代目車両。3列シートの採用などで、車内環境が大幅に向上
「ムーンライト号」の2代目車両。3列シートの採用などで、車内環境が大幅に向上
1983(昭和58)年に登場した「ムーンライト号」という高速バスを、覚えている方もいるでしょう。大阪~博多間を結んだ夜行バスですが、あまりにも画期的だったため、デビュー当時は大きなニュースとなりました。646kmという日本最長距離路線であることに加え、バスゆえの安い運賃ながら広いシート、トイレ・サービスコーナー付きという車内環境を誇りました。
ちょっと視点を移して企業戦略として見た場合、「ムーンライト号」は福岡県の西鉄バスと大阪府の阪急バスの2社という、目的地同士のバス会社による共同運行で、これは、それまでにない斬新な発想の運行形態でした。現在運行されている長距離の高速バスは、この運行方式が一般的ですので、今日の高速バスのパイオニアとも言えます。
西鉄バスのアイデアの数々
 都市高速を走る一般型バス車両は、福岡らしい光景です
都市高速を走る一般型バス車両は、福岡らしい光景です
そんな個性的な「ムーンライト号」を生んだ西鉄バスですが、西鉄バスが実際にこれまでに行ってきた施策は実に多彩です。ガイドウェイに導かれるガイドウェイバス、リバーシブルレーン(バス専用レーン)、深夜バス、100円循環バスなど、どれも利用者目線で編み出されたバスばかり。現在でも、例えば福岡都市高速を路線バス仕様のバスが走っている光景に出くわしますが、ほかの都市ではあまり見られない光景です。都市高速は高速自動車道ではないためシートベルトが無い一般のバスも走行が可能で、おかげでバスがスイスイと市内を駆け抜けていきます。実は、かつて東京でも同様のバスが運行されていましたが、渋滞による遅延によって定時運転が難しく廃止されています。
このほか、女性運転士の採用、高速バス予約センター、貨客混載のバス小荷物など、ソフト戦略も西鉄バスでは早々に実施されていました。
バスと鉄道の相乗効果 九州らしい、個性豊かな乗り物へ
 鉄道とともにバスも進化する九州。まるで走る応接間のような福岡高速ラグジュアリーバスの車内
鉄道とともにバスも進化する九州。まるで走る応接間のような福岡高速ラグジュアリーバスの車内
今では全国のバスで行われている運転士による声かけや、赤信号中のアイドリングストップなども、西鉄バスでは1970年代から実施されていて、これが九州全般のバス会社に広まったと言われています。
こうして九州はどこへ行くにもバスがとても身近な存在になっているわけですが、九州内の新幹線、特急や普通列車の車両が次々に個性的に生まれ変わっている背景には、こうしたライバル関係にあるバスの存在も一因です。実は、これも現在進化中で、線としての鉄道と、面としてのバスという役割分担を行うMaaSが始まっています。バスと鉄道が手を組み、利用者にとってより便利な移動手段になりつつあります。
今年、2022(令和4)年は西九州新幹線の開業を控え、注目一途の九州。往復で鉄道+バスと乗り比べてみると、その個性が際立って感じられることでしょう。